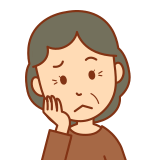
和室にある天袋の利用方法がよく分かりません。
何となく使っていない物を入れているだけ。
せっかくなので活用方法を知りたいですね。
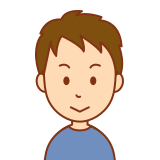
よく分かります。天袋って高いところにあるし、収納的に狭そうだし・・・。
でも、安心してください。
天袋に特化した収納アイデアをまとめてみました。参考になればと思います。
天袋とは?・・・天袋の基本イメージとその活用法
天袋って何?押入れとの違い
天袋(てんぶくろ)とは、和室や収納スペースに設けられる収納のひとつで、天井付近に設置された吊り戸棚のような構造をしています。特に日本の住宅に多く見られ、押入れの上部に設置されていることが多いのが特徴です。
押入れとの主な違いは、その「高さ」と「用途」にあります。押入れは布団や衣類など、日常的に出し入れするものを収納するのに対し、天袋はその位置の高さから「頻繁に使わない物」の保管に適しています。たとえば、季節行事に使用する装飾品や、記念品、アルバムなどが典型です。
また、天袋は洋室のクローゼットにはあまり見られず、主に和室や昔ながらの日本家屋に見られる収納形式という点も押さえておくとよいでしょう。
天袋のサイズや特徴
天袋のサイズは住宅によって大きく異なりますが、一般的には高さ30cm〜50cm、奥行き40cm〜60cm、幅は押入れや壁面と同じく90cm〜180cmほどが多く見られます。
建築時期や建築様式によってサイズが異なるため、実際に収納を行う前には正確な寸法を測ることが重要です。
最大の特徴は「手が届きにくい高さ」にある点です。そのため、脚立や踏み台が必須となり、収納や取り出しにはひと手間かかります。このことから、「軽くて壊れにくく、長期間使わない物」の収納が向いているといえるでしょう。
また、天袋は気密性がやや低く、外気の影響を受けやすいため、湿気や温度変化に弱い品物の保管には注意が必要です。密閉容器や防湿剤の併用が効果的です。
天袋を上手に活用する
天袋は「物置」になりがちなスペースですが、工夫次第で非常に有効な収納空間になります。
活用法の第一歩として、「使用頻度の低いもの」に絞って収納品を選ぶことが重要です。
例えば、以下のようなアイテムが天袋収納に向いています。
・ アルバムや子供の作品、思い出の品
・ 旅行用の大型バッグやスーツケース
・ 来客用の予備布団や毛布
・ 替えのカーテンやラグ、クッションカバー
次に、収納する際のポイントは「ボックスやケースで分類・保護」することです。100均やホームセンターで販売されている収納ボックスを活用すると、中身が一目で分かりやすく、出し入れもスムーズになります。
また、収納ラベルを貼っておくと、後で探すときに迷うことがなくなります。ボックスの色や形を統一すると、見た目もすっきり整い、天袋内が整然とした印象になります。
収納順も重要で、「重くて大きい物は奥に、軽くて取り出しやすい物は手前に」が基本です。上から見下ろすようにして取り出す形になるため、頻繁に使うものを奥にしまってしまうと、出し入れが大変になります。
天袋収納に関する注意点
天袋を利用する際にはいくつかの注意点があります。
最も重要なのは「安全性」です。
高所での作業になるため、無理な体勢で荷物の出し入れをしないように注意しましょう。安定感のある脚立や踏み台を使用し、片手で荷物を持ちながらもう一方の手で体を支えるといった行動は避けるべきです。
「収納物の重さ」にも注意が必要です。
天袋の棚板は一般的に厚さが薄く、過度な重量をかけるとたわみや破損の原因になります。収納ボックスに詰め込む前に、収納全体の重量を意識することが求められます。
長期間開け閉めしないことで、ホコリが溜まりやすいのも天袋の特徴です。年に1〜2回は中身を確認し、換気や掃除を行うことで、カビや害虫の発生を防ぐことができます。さらに、防虫剤や除湿剤の定期的な交換も大切です。
加えて、湿度が高くなりがちな夏場や梅雨時には、収納品が劣化しないよう、通気性の良い素材の袋を使う、新聞紙や乾燥剤を併用するなどの工夫をすると良いでしょう。
このように、天袋は高さというハンデはあるものの、工夫と注意を払えば、家庭内で不足しがちな収納スペースを有効に使える貴重な場所となります。
天袋に収納するアイテム
布団や寝具の収納方法
天袋は使用頻度の低い布団や寝具の保管に適した場所です。
特に来客用の布団や、季節によって使い分ける掛け布団、毛布、敷きパッドなどを収納するのに便利です。ただし、高所にあるため重量がある布団は出し入れが難しいため、軽量タイプの布団や圧縮袋を活用するのが効果的です。
収納の際は、まず布団を天日干しまたは布団乾燥機で乾かしてから保管することが基本です。湿気がこもりやすい天袋では、乾燥が不十分だとカビやダニの温床になる可能性があるため、除湿剤と一緒に収納することが推奨されます。また、布団は通気性のある不織布の収納袋に入れることで、湿気をこもらせずにホコリや虫の侵入を防げます。
圧縮袋を使う場合は、密閉後に空気の逆流を防ぐため、密封性の高いタイプを選びましょう。圧縮した布団は平らにして積み重ねると、天袋のスペースを有効に使えます。収納後は収納年月日や内容をラベルで明示しておくと、次回の取り出し時に役立ちます。
季節ごとの衣類の収納
天袋は、オフシーズンの衣類を保管するのに最適なスペースでもあります。
特にかさばる冬物のコートやニット類、反対に夏用の薄手の衣類や水着など、季節ごとに使用しないアイテムをまとめて保管できます。
収納の基本は「洗濯済みであること」。
着用後の汗や皮脂が残っていると、黄ばみやカビの原因になります。洗濯・クリーニングの後はしっかり乾燥させてから、シワを伸ばしてたたみ、収納ボックスや衣類用収納ケースに分類して入れましょう。
衣類の種類や素材によっては、防虫剤の選び方にも注意が必要です。ウールやシルクなど虫害を受けやすい素材には、天然由来の防虫剤(ヒノキやラベンダー系)を活用するとよいでしょう。さらに、空気の通り道を確保するために、衣類の上に新聞紙を1枚敷くなどの工夫も有効です。
衣類の収納は、頻度別や季節別、または使用者ごとに分けると管理しやすくなります。ラベリングや色別ケースを使って収納内容がひと目で分かるようにすると、取り出しの手間も軽減されます。
おもちゃや小物の収納アイデア
子どもが成長して使わなくなったおもちゃや、思い出として取っておきたい小物類は、天袋に保管しておくと便利です。普段使用しないアイテムであれば、日常の動線に干渉せず、空間を有効活用できます。
収納のポイントは「分類」と「緩衝材の活用」です。
おもちゃは素材や形状によって破損のリスクがあるため、緩衝材(プチプチやタオルなど)で包んでから収納ボックスに入れると安心です。たとえば、プラスチック製と木製のおもちゃを同じケースに入れると擦れによって傷がつくことがあるため、別々に分けておくとよいでしょう。
また、小物類(記念品、ハンドメイド作品、卒業アルバム、作品ファイルなど)は、書類ボックスやフォルダーケースを使うと形を保ったまま保管できます。アルバムや紙製品には防湿・防虫の対策が必須で、除湿剤を同封するほか、定期的に状態を確認するようにしましょう。
旅行用のスーツケースも収納
旅行用のスーツケースは大きくかさばる上に、使用頻度も低いため、天袋の収納にはぴったりのアイテムです。
収納前にはスーツケースの中を空にして、内側を乾拭きして消臭し、必要があれば除菌スプレーなどで清潔に保ってから保管します。また、収納中に型崩れしないよう、空の状態でも中に緩衝材や新聞紙を詰めておくとよいでしょう。
スペースを有効に使うには、スーツケースの中に小型のバッグや旅行グッズ(アイマスク、変換プラグ、ポーチ類)などを入れておく「入れ子式収納」が効果的です。これにより、天袋の限られた空間でも多くの物を整理して収納できます。
天袋の湿気対策とカビ防止
通気性を考えた収納アイデア
天袋は高所に位置しており、空気の循環が悪くなりやすい構造上、湿気がこもりやすい傾向があります。湿気がこもることでカビが発生しやすくなります。これを防ぐには、通気性を確保することが大切です。
通気性を高めるための方法として有効なのが「収納ケースの選び方」です。密閉型のプラスチックボックスではなく、通気口付きや不織布素材の収納袋を使用することで、空気の流れを妨げずに収納物を守ることができます。
収納物同士の間に少しの隙間を作ることも大切です。詰め込みすぎると空気が通らなくなり、湿気が滞留する原因になります。
収納空間全体を定期的に換気することも有効です。年に数回は天袋を開放し、風を通すとよいでしょう。これにより湿気を逃がし、空気の流れを改善できます。
収納物に合わせて新聞紙やシリカゲルなどの乾燥材を活用するのも効果的です。新聞紙は吸湿性が高く、収納物の下や隙間に敷くだけで湿気の蓄積を防ぐことができます。
すのこを使った湿気対策
すのこは、天袋における湿気対策の代表的なアイテムです。
すのこを敷くことで収納物の底面と棚板との間に空気の層を作り、通気性を大きく改善することができます。
特に木製のすのこは調湿性に優れており、湿度が高いときには吸湿し、乾燥時には放湿する働きがあります。棚の幅や奥行きに合わせて複数枚を組み合わせると、スペースを有効に活用できます。
すのこの上に収納ボックスを置く場合には、滑り止めシートを併用するとズレを防止でき、安全性が高まります。また、すのこの隙間を活かして除湿剤を差し込んでおくと、さらに効果的な湿気対策が実現します。
最近では、プラスチック製のすのこも登場しており、軽量かつ耐久性があり、カビや虫に強いというメリットがあります。設置後は定期的にホコリや汚れを拭き取り、清潔な状態を保つことで効果が持続します。
防カビシートの効果と使い方
防カビシートは、天袋内のカビの発生を未然に防ぐための便利なアイテムです。
防カビ成分が加工されたこのシートは、敷くだけで表面に付着した湿気を吸収し、カビの繁殖を抑制してくれます。
使用する際は、天袋の底や壁面、天井にぴったりと敷き詰めるのが効果的です。特に収納物と棚板が直接触れ合う部分に敷くことで、空気の通り道を確保しながら、カビの発生を防止できます。
防カビシートは、種類によって効果の持続期間が異なります。一般的には3ヶ月〜6ヶ月が目安となっており、定期的な交換が必要です。ラベルを貼って交換日を記録しておくと、管理がしやすくなります。
まとめ
もちろん天袋の存在は知っていましたが、「天袋って何を入れるの?」とずっと思っていました。
母が何かを入れているというのはおぼろげながら覚えていたのですが、高い場所にあるので、ついそのままにしていました。
でもある日、脚立を持って来て天袋を覗いてみたんです。
そしたら、折りたたみのマットレスが1つだけ入っていました。当たり前なのですが、天袋の中はスカスカなので、何だかもったいないと思ったのが、天袋の収納を考えるきっかけになりました。
天袋って使い方次第で本当に便利な収納スペースになるということ。たとえば、軽くて使用頻度の低いものを収納するだけでも、他の収納に余裕が生まれるんですよね。収納ケースを使えば出し入れもラクになりますし、除湿剤やスノコを使えば湿気対策もバッチリ。
もちろん、高い位置にあるので脚立や踏み台は必須ですが、安全に気をつけて定期的にチェックする習慣をつけるようになってからは、天袋も我が家に欠かせない収納のひとつになりました。年に何度かの見直しで、忘れていた物との再会も楽しみのひとつになりました。
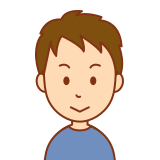
天袋も利用の仕方ひとつでその存在が大きく変わります。
少し視点を変えて、天袋を見直してみるのはいかがでしょうか。


