子どものおもちゃの片付けと収納とは?
子どもがおもちゃを片付けない悩み
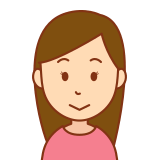
いくら言っても子供がおもちゃを片付けてくれません。
どうしたらいいのでしょうか。
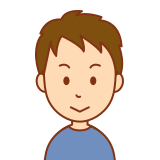
子どもがおもちゃを片付けない問題に悩む家庭は少なくありません。
せっかくきれいに片付けても、数分後には部屋中におもちゃが散らかっている……そんな光景は日常茶飯事です。
この悩みの原因は、子どもにとって「片付け」が難解で、どこに何をしまえばよいのかが分かりづらいことが多いからです。
大人が使うような収納方法は、子どもには不向きな場合もあります。また、遊ぶことに夢中で、片付けまで意識が向かないというのもよくある理由のひとつです。
子どもがおもちゃを片付けるようにする秘訣は?
子どもが自発的におもちゃを片付けるようになるためには、まず「片付けは楽しいこと」「自分でできること」という意識を育てることが大切です。
片付けをゲーム感覚で行ったり、声かけの際に「おもちゃのおうちに帰してあげようね」など、子どもの想像力をくすぐる言い方をすると効果的です。
片付ける場所がひと目でわかるようにラベルを貼ったり、イラストを使って視覚的に分かりやすくする工夫もおすすめです。片付けるという行為を、生活の中の「楽しい習慣」として取り入れることが、長続きのコツになります。
おもちゃのジャンル別収納ボックスで片付け
おもちゃを片付けやすくするためには、ジャンルごとに収納ボックスを用意するのが効果的です。
「ブロック」「ぬいぐるみ」「ままごとセット」「絵本」など、種類ごとに分けて収納することで、子どももどこにしまえばよいかが分かりやすくなります。
ラベルやイラストを使って「見て分かる収納」を意識することで、片付けのハードルを下げることができます。ボックス自体も子どもの手が届く高さや持ち運びやすい軽さを意識して選ぶと、自分から動きやすくなります。
子どもの成長に合わせたおもちゃの片付けと収納
子どもは成長とともに興味の対象が変わり、おもちゃの種類も変化します。そのため、収納方法も年齢や成長に合わせて見直すことが重要です。
乳幼児期は安全性を第一に、角のない柔らかい収納を使う、就学前は自分で出し入れできるよう高さを調整する、小学生になると分類や整頓を意識した収納に移行するなど、段階ごとの工夫が必要です。
遊ばなくなったおもちゃは定期的に見直して手放すようにすると、収納スペースに余裕が生まれ、整理整頓のしやすさも保てます。子どもの「今」に合わせた収納の工夫が、快適で片付けやすい空間づくりにつながります。
大量のおもちゃを減らして収納する方法
子どもと一緒に全部のおもちゃを出す
大量に増えてしまったおもちゃの整理をするには、まずは子どもと一緒に全てのおもちゃを一度出してみることが第一歩です。
棚や引き出し、収納ボックスなど、すべての場所からおもちゃを取り出して並べてみると、どれだけ持っているかが一目で分かります。
この作業には時間がかかるかもしれませんが、親子で「見える化」することで、必要なものとそうでないものを冷静に判断できるようになります。子どもにとっても、自分の持ち物を見直す良い機会になります。
出したおもちゃを子どものお気に入り度で分類する
おもちゃを出し終えたら、次は子どもに「どれが好き?」「最近遊んだのはどれ?」と問いかけながら、お気に入り度に応じて分類していきます。
「毎日遊ぶもの」「ときどき遊ぶもの」「あまり遊ばないもの」といったグループに分けることで、どれを手放すか、どれを残すかの判断がしやすくなります。
子ども自身に選ばせることで、自分の意思を尊重されたという実感が得られ、片付けに前向きになりやすくなる効果もあります。
子どもお気に入りのおもちゃだけを元に戻す
分類が終わったら、最後に「お気に入り」のおもちゃだけを収納場所に戻します。
収納スペースに限りがある場合は、「ときどき遊ぶもの」も季節ごとにローテーションで入れ替える仕組みにすると、常に新鮮な気持ちで遊ぶことができて一石二鳥です。
遊ばないと判断したおもちゃは、思い切ってリサイクルに出したり、必要としている人に譲るのも良い方法です。
こうしたサイクルを定期的に取り入れることで、おもちゃの量を無理なく減らしながら、スッキリとした収納が維持できます。
子どもの成長に合わせたおもちゃの片付け
使わなくなったおもちゃの処分方法
子どもの成長とともに、おもちゃの関心や使い方は大きく変化します。かつて夢中で遊んでいたおもちゃも、ある日突然まったく使われなくなることも珍しくありません。
そんなときは、潔く「使わなくなったおもちゃ」を処分する決断が必要です。処分といっても、ただ捨てるのではなく、リサイクルショップに持ち込んだり、寄付やフリマアプリを活用するなど、次の使い手につなげる方法を選ぶのがおすすめです。
子ども自身に「もう使わないから誰かに譲ろうね」と伝えることで、物を大切にする気持ちや人に譲る優しさを育むきっかけにもなります。
おもちゃ収納の見直しと変化
おもちゃの収納方法も、子どもの成長段階に応じて変えていくことが求められます。
幼児期は安全性を優先して柔らかい布製ボックスや蓋なし収納が便利ですが、成長するにつれて細かいパーツやセットものが増えるため、仕切り付きの引き出しやラベル付き収納が有効になります。
小学校入学後は、おもちゃだけでなく文房具や勉強道具との兼ね合いも考えた収納が必要になります。子どもの「使いやすさ」や「管理しやすさ」を意識して、収納場所や方法を段階的にアップデートすることが、片付けの習慣づけにもつながります。
子どもの年齢別に合わせた片付けのポイント
年齢に応じた片付けの教え方も大切です。2〜3歳ごろは「箱に入れる」などの簡単な動作からスタートし、5歳前後になると「仲間ごとに分けて入れる」ことができるようになります。
小学生になると「遊び終わったら元に戻す」というルールを守ることができるようになるため、親は一緒にルールを確認しながら見守ることが重要です。
年齢が上がるにつれて、子どもにとっての「自分のスペース」を持たせることで、責任感や整理整頓の意識が自然と育まれます。このように、段階的なサポートを心がけることで、片付けが習慣となり、将来的に自立した生活にもつながっていきます。
まとめ
我が家でも、かつては毎日のようにおもちゃが部屋中に散乱していて、常に片付けに対してストレスを感じていました。
でも、子どもと一緒におもちゃを全部出してみて、一つひとつ「いつも遊んでいるか」「好きか」を確認しながら分類するようにしてから、驚くほどスッキリ片付きました。
収納も見直し、子どもが自分で片付けられる工夫をしたことで、今では「片付け」が習慣に。成長に合わせて見直していくことが、無理のない片付けのコツだと実感しています。


